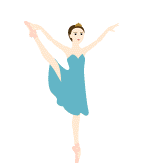|
バレエの歴史もわかりやすく説明しておきましょう^^
バレエといったらフランスやロシアを思い浮かべる方が多いと思いますが、起源は
イタリアにあるとされていて、15世紀の中世イタリアの貴族の舞踏会がそれだと
言われています。そして、この時期に「バレエ」という言葉が生まれました。イタリア語では
踊ることをバラーレ(ballare)と言い、これがバレエの語源になっています。
このバラーレから舞踏会・宴会を意味するバーロ(ballo 仏語の bal、英語のballの語源)という語が生まれ、15世紀には、そこからバレット(balletto)という語が派生して、これが後にバレエ(ballet)になりました。
それがフランスに渡り、フランス宮廷と共にバレエは栄えていきました。
特に「太陽王」と呼ばれたルイ14世は自らバレエを踊り、1661年に王立アカデミーを創設、間もなく建設されたパリ・オペラ座を舞台に数々のバレエを演じました。
「太陽王」という名前は、ルイ14世が劇の中の太陽の役を好んで踊っていたことから
名づけられました。
この頃は、バレエは男性が踊るもので、女性の役は男性が女装をして踊っていました。
ルイ14世が太りすぎでバレエを引退した頃から、舞踊を職業にする、
いわゆるバレエダンサーが現れ始め、女性ダンサーも出てきました。
舞台も宮廷から劇場へと変わっていったのです。
19世紀に入ると、今と近いバレエが踊られるようになり、ハイヒールとドレスという
衣裳が、トウシューズとチュチュに変わっていきました。
トウシューズで最初にバレエを踊ったのは、マリ・タリオーニというダンサーでした。
(詳しいことはトウシューズって何?をご覧になってください^^)
このころに確立されたバレエを「ロマンティック・バレエ」と呼び、
「ジゼル」や「ラ・シルフィード」という作品が生まれました。この頃の特徴は、
物語は心情的なものを表現するものが多く、チュチュは裾の長い円錐形に広がる
ロマンティックチュチュが主流なことです。
この頃から、バレエは主に女性のものになっていきましたが、それと並行して、
バレエは男性が女性の体、そのころはドレスに隠されていた女性の肢体を鑑賞するための芸能になっていったのです。さらに劇場は、愛人を探すお金持ちの男性と、パトロンを探す
女性ダンサーたち(ほとんど下層階級の出身でした)との出会いの場と
化してしまい(今でいうキャバクラのようなもの)、当然ながらバレエの芸術的水準は低下の一途を辿っていきました。
しかしそれはフランスやイギリスなどのヨーロッパの話で、フランスでバレエが堕落して
いった頃、ロシアでは皇帝が莫大なお金を注ぎ込み、フランスから著名な
振付家・教師を招いてバレエを広めていき、その甲斐あって、19世紀後半になると
ロシア・バレエの水準はフランスを追い越しました。そして、先に述べたようにフランスで
バレエがエロティックな見せ物に堕落していた頃、ロシアでは新しい美学と様式を持った
バレエが完成されました。これが「クラシック・バレエ」と呼ばれるもので、その確立者は
「白鳥の湖」や「眠れる森の美女」を振付けた、フランス人のマリウス・プティパでした。
プティパの確立したクラシックバレエは、ロマンティック・バレエとは違って、「舞踊による劇」という色彩が薄れ、もっぱらマイム(身振り)で進行する劇の部分と、劇の進行とは直接無関係な純粋舞踊の部分とが分けられ、言い換えると、劇的内容はどうでもよくなり、ストーリーは踊りを見せるためのアリバイのようなものになったのです。クラシック・バレエの
代表作は「眠れる森の美女」ですが、プティパはその他にも「白鳥の湖」「バヤデルカ」
「ドン・キホーテ」「海賊」など、数多くの作品を残しました。
この頃に誕生したのが、バレリーナの足をより美しく、よりテクニックを見せられる
ように、裾が短く傘のように広がったクラシックチュチュです。
20世紀に入ると、今度はまた新しい動きが出てきます。ニジンスキーなどの、今までの
バレエの枠を取り去った新しい作品を作る振付家やダンサーが出てきたのです。
「薔薇の精」や「牧神の午後」が代表的な作品です。
それが現代のモダン・ダンスやコンテンポラリー・ダンスに繋がっていったのです。
モダンやコンテンポラリーはバレエの枠を超え、より自由な動きや表現を
追求していったものですが、バレエとモダン・ダンスなどはお互いに影響しつつ、
成長していっています。現在でも古典バレエは非常にたくさんの
バレエ団によって上演され、世界中の人たちに愛されています。
|